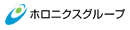脳動脈瘤
最近、私のささやかな論文が「脳卒中」という雑誌に載りました。(脳卒中20..286-292,1998)
『脳動脈瘤、あるいは漏斗状拡大が多発した一家系について』というタイトルです。
近くの町の8人兄弟のうち、3人に脳動脈瘤ないし、漏斗状の拡大を認め、手術をしたのです。脳動脈瘤の家族内発生については、これまで多くの報告がなされ、脳動脈瘤の発生部位、多発率、男女比、発症時年齢差、遺伝的背景などについて検討が加えられてきました。
具体的には
①…女性の比率が高い。
②…平均42・3歳など、比較的若くして破裂する。
③…兄弟、姉妹では同部位、あるいは対側の同部位(mirror site)に発生することが多い。
④…兄弟どうし同年代に破裂すること。
⑤…動脈瘤形成後、短期間のうちに、サイズが小さくても破裂しうること。
⑥…脳動脈瘤の多発率は19.9-40%で、一般の16.3%に比べ高い。
など、一般の脳動脈瘤とは異なる特徴が指摘されていますが、その全てが明らかになっているわけではありません。
いつものように自分の経験した症例を吟味した上で、過去の文献のエッセンスを加えた症例報告を行ったのですが、これまで、原稿が一回で受理されたことはありません。
審査委員の先生の厳しいチェックが入って、少なくとも1~2回は突き返されますが、私自身、いくつかの原稿が没になった経験も持っています。
一方、彼等自身はそれをみじんも厳しいなどとは思っていないでしょう。
いいかげんな採択基準では雑誌の質は落ちるし、投稿者を甘やかしてもろくなことはありません。
日々の多忙な診療の合間をぬって文章を書き、高額な文献検索と術中写真などの写真を整えたあげく、不採用で返されてくるのはなかなかにつらいものがあります。しかし自分の力量のせいでもあり、致し方ありません。
私の場合、これまでに全国誌に載ったのが15編。
たかが15編にすぎないし、私の言は時に大げさなのですが、私にとっては人生のmile stoneとして,ひとつの宝物でもあると言えば言いすぎでしょうか。
後世に残って他の論文に引用されたら、これにまさる喜びはない、という人もいますが、私の論文は我ながら深みに欠けるので、その期待はうすいでしよう。
そもそもなぜ人は論文などというややこしいものを書くのでしょう?
論文といっても我々の世界ではリサーチ的なものや、総説的なものは価値があり、症例報告については「なんや症例報告か」というように、やや下にみられているようです。
私の場合、総説的なものが一編で、あとは症例報告です。学間的価値としては、重要度は低いと言われるでしょう。
しかし、私のボスである木下和夫教授はよく、我々に向かって話したものです。
『症例報告こそ書きなさい。それは君達の、疾患に対する理解の集大成を世に間うことで
あり、また、様々な臨床的事実の裏付けがなければ書けないからだ。』と。
そういうわけで、ボスの信奉者である私は、せっせと論文作成に励んでいるのです。もっとも「はげむ」などと、またまたえらそうに言うなら、200編ぐらい書いてから言えよ!ということでもあります。
ちなみに母校の第一外科の教授選挙にでた人は、実際に200編も書いていたそうです。
この数字自体はやはり、ひとりの医者が書く数としてはたいしたものでしょう。医者は毎日、論文だけ書いて暮らしているわけではないからです。
200といってもほんとうのところ誰が書いたかわからん!という人もいるでしょう。たとえばデータ集めや学会での発表は部下がして、論文のタイトルだけは自分の名前を最初にもってくるボス連中がいるという古典的な話があるからです。
ぱらぱらと散発的に書いていながら、朱玉の名論文を連発しているかのごとくふるまうのは、あつかましい限りだという意見もありましょうが、手術やベッド サイドの仕事が目の回るような忙しさになるにつれ、心のなかに、「なんのためにくたくたで休みたい時間を費やしてまで、あるいは予供とボール蹴りをする時 間を使ってまで論文を書くのか」という問いが生まれるようになりました。
大学人ならともかく、民間病院にいて学間の世界にいるわけではない私が、症例報告ごときを書いて何になるというのでしょうか。
時間があり余っているならともかく、私はいったい何をしているのでしょう。
だれが褒めてくれるわけでもないのに。
そんな折り、ふたりの先輩の言葉のなかに心の晴れ渡るような文句を見つけました。
ひとつは川崎医大の我が敬愛する原田種一教授が、東京の伊藤病院勤務時代、「ただ、書くために論文を書いた」時期があると聞き、何かがふっきれたのを覚えております。
さらに、脳神経外科ジヤーナル2月号(vol' NO' 2,1998)にあった。静岡県立総合病院、脳神経外科部長、花北順哉先生の言葉は私をどれだけ元気づけたかわかりません。
以下先生の言葉を正確になぞってみます。
『今までに何度か若い先生方から聞かれたことのひとつに「なぜ、論文を書くのですか」との質間があります。いくつかの答えをしてきました。時には、「臨床 家は確かに診断が正確で手術手技が優れており、術後の管理に落度がなければ、まずは及第と思われるが、臨床家の評価は客観的には困難なものがあり、これの 評価を求めたい時には学会発表や臨床論文があるのではないか。もっとも、話すことと、やっていることが大違いなどは間題外だが」と答えたことがあります。 またある時は、「患者は最高の教科書である。症例報告をあまり重視しない風潮があるがまったくの間違いである。自分で教科書の一章を書き上げるようなつも りで症例報告は行えばよい。症例報告を書くためには先人の知見をすべからくみ取る必要があり、結局は自分の知識の整理、知見の拡大になる。結果的に他人が それを読んで参考にしてくれるか否かは本来はどうでもよいことだと思う」とはげましたこともあります。読者諸氏はどのように考えますか。この頃は私自身、 依頼原稿ばかりで自ら取り組んで書くことがきわめて少なくなってきました。物事に対して感動することが少なくなり、怠け心が蔓延しているものと我ながら恥 じ入る次第です。最近さる学会で引退間近のある老教授が、少ない聴衆を前に熱心に症例報告をしておられるのを拝聴したことがありました。「いまさら何で、 研修医にでもさせればよいのに」とのっぶやきも聴かれましたが、熱心に楽しそうに語しておられる姿を拝見して、なんとも羨ましいことだと思いました。会議 に明け募れたり、マネジメントに精を出すのも立場上必要かもしれませんが、生涯一学究が理想の姿と考えております。昨今の風潮として、impact factorの高い雑誌に掲載された基礎的研究が評価されて、臨床家の書く臨床論文はきわめて評価が低いのが残念ながら事実のようです。生身の人間を相手 とする臨床医学でこのような傾向がのぞましいことなのでしょうか。将来、手痛いしっぺ返しを受けなければよいがと危倶します。今後もきらりと光る臨床論文 を各世代の先生方から応募していただけることを、楽しみにしております。』
一方、とにかく書けばよいということに対して、異常に嫌悪感を抱く人々がいるのも事実です。私には彼等の気持ちがよくわかります。確かに駄文、駄作が公 器としての脳神経外科の雑誌に載ることは許されないでしょう。また、間違った記載は読む人を惑わすでしょうし、読者の貴重な時間を奪ってしまうでしょう。
かつてある巨大病院の脳神経外科部長と会食する機会があり、私の書いたいくつかの論文を差し上げたが、彼は手紙だけを一瞥し、顔をしかめながら、手にとろうともしませんでした。
彼によれば、論文などというものは、教授の許しを得て、何人もの中間チェックが入って初めて世に出るべきものだということで、彼の目には私のものなどはそうでないように映ったらしいのです。彼の態度は一面で正しいのです。
だからこそ論文採用のための審査があるじやないかとも言えますが、ほんとうのハードルは実は我々投稿者の心のうちにあるのでしょう。
学問的根拠のうすい、あいまいな記載をうやむやのままにして提出しても、幾度かは審査委員の目をごまかせるかもしれないからです。
こんなことを今さら書くのも恥ずかしい限りではありますが、論文は自慢大会の場ではなく、自己規制、学間的良心の中から生まれてくるものだということです。
国立循環器病センターの菊地晴彦総長によれば、わが国では人口三万人あたりひとりの脳神経外科医がいて、ある疾患に対し、まとまったシリーズの発表が出ず、症例報告や外科解剖の発表が中心であるとされています。
だからこそ、私のような前線の中隊長クラスにも発表の場があるのだとも言えるでしょう。
さて、それにしてもです。
なぜ、私は論文を書くのか、です。
①…医療者として、脳神経外科のなかで自己の存在をアピールしたいという欲求か。
②…ただ、書くことが好きなのか、あるいは酒を飲むよりは論文を書くことを選んだだ
けのことか。そういえば、最近、朝日新聞に次のような記事が載りました。「文章を書き
たがる人が増えている」という内容です。記事によれば、パソコンの普及が、書くこと
、発表することをより身近にし、自己発現がしやすくなったとしています。この時代に
皆、他者でない自分を、自分のよって立つところをつかみたがっているのかもしれません。
③…将来、娘や息子が成長した折りに、パパはこーんなことをして、がんばっていたん
だよ、と自慢したいからか。
④…後世の論文に自分の論文が引用されることを夢見てか。
⑤…脳神経外科の世界も他の医学の領域と同様、個々の症例の積み重ねがあって初めて
ある疾患に対し、いくつかの法則性が明らかになり、それらが治寮に結び付いていく
ことが多い。であれば、自分のささやかな論文がその一助になるのではないか。
⑥…教授の教えを忠実に守っているだけか。
⑦…やはり、がんばっている自分を楽しみたいという自己愛の発露のひとつか?。
しかし実際はなぜ、論文を書くのかについて、わがことながら、ほんとうのところはわからないのです。わからないが、私なりにひとつ手応えを感じていることがあります。
それは、脳神経外科コングレスのモットーでもあるのですが、「ANCORA IMPARO」「俺は今でも勉強しているぞ」ということです。
私はかねてから勉強は苦手でありましたし、今、こうして文献をひもとき、脳神経外科の勉強をしていると、ふつふつと沸き起こるような満足感をおばえます。
ある一瞬、一瞬は先に挙げた項目の、そのいずれの要素をも順番に自覚しているのです。
したがって、論文を書くという動機はより総合的かつ複雑なものと言えるかもしれません。
たしかに自分の論文が人の目に触れることは素直にうれしいものです。別刷りが私の手元に届いたときのうれしさはなんともいえないものがあります。そして、ふと、この高揚はいったい何なのだという戸惑い、かくして先ほどからの疑間と命題に逆戻りしてしまうのです。
夜、うちに帰って原稿を書いていると4歳の息子が寄ってきて横にならんで座り、いっちょまえに字の練習などをはじめます。その姿はかぎりなくいとしい、と臆面もなく思います。
そう、私の書く論文が、なにほどか他者に影響しているとすればまさにこれだったのです。
おお、わが息子よ。「ANCORA IMPARO」「俺は今でも勉強しているぞ」。
現在、当院の脳神経外科は脳神経外科専門医訓練施設として、児島地区の脳神経外科疾患で困っていらっしゃる患者さんを診させていただいております。
今後もさらにきめ細かい診療が出来ればと考えております。
『頭痛』や『めまい』、『手足のしびれ』、『物が二重に見える』など、日常生活の中で気づかれたことをお気軽にご相談ください。
木村 知一郎 (副院長、脳神経外科部長)
倉敷市児島小川町3685番地
TEL 086-472-1611
FAX 086-474-3148
webmaster@kojimach.or.jp webmaster@kojimach.or.jp 086-472-1611